
こんにちは、りんむです。
日本昔話って何かしら教訓ありますよね。
息子に伝えたい事あるとき、その教訓入った絵本をこっそり読んでます 笑
昔話って、ただの“お話”じゃない。
こどもに伝えたいこと、大人が忘れかけていたことが、そっと語られている気がします。
「やさしさって何?」
「正直でいるってどういうこと?」
そんな感性を、物語を通してこどもに届けてみませんか。
今回は、子育てに役立つ日本昔話を10話選び、それぞれのあらすじ・教訓・連想される四字熟語をやさしくまとめました。
親子で読んでも、大人が心の整理に使っても、きっと何かが響くはずです( *´艸`)
わらしべちょうじゃ

ある日、貧しい男が「最初に手にしたものを大切に持っていれば、幸運が訪れる」という夢を見ます。
目覚めて最初に触れたのは、一本のわらしべ。男はそのわらしべを持って歩きながら、出会った人に親切にし、物々交換を重ねていきます。
わらしべはみかんになり、ぬのになり、馬になり…と、次々に価値あるものへと変わっていきます。
そのたびに男は誠実に人と関わり、困っている人に手を差し伸べていきました。
最後には立派な屋敷を手に入れ、貧しかった男は長者となりました。
【🌱 教 訓 】
・素直に人の助言を聞くことが出来る人は強い。
・親切や誠実な行動が、思わぬ幸運を呼ぶ。
・チャンスは行動する人に訪れる。
【🪶連想する四字熟語 】
🔶温良優順(おんりょうゆうじゅん)
意味:穏やかで優しく、素直な性格。
→主人公の人柄そのもの。人に親切にし、争わず誠実に行動する姿。
🔶善因善果(ぜんいんぜんか)
意味:良い行いが良い結果を生む。
→親切にしたことで、次々と幸運が訪れる展開。

これに似たお話、世界中にあるみたいだね!
逆パターン(どんどん低い物へ変わっていく)のお話もあるみたいだよ!
かさじぞう

雪の降る大晦日。貧しいおじいさんとおばあさんは、お正月の準備もままならず、少しでもお餅を買うために、おじいさんは笠を売りに町へ出かけます。
けれど笠は売れず、帰り道で雪をかぶった6体のお地蔵様に出会います。
おじいさんは売り物の笠をお地蔵様にかぶせてあげ、最後の1体には自分の手ぬぐいを巻いてあげました。
その夜、老夫婦の家の前に米俵や餅、野菜などのごちそうが積まれていて、遠くには6体のお地蔵様の姿が…。
善行へのお礼として、お地蔵様が贈り物を届けてくれたのでした。
【🌱 教 訓 】
・他人を慈しむ心は、自分に返ってくる
・本当の心の豊かさとは、他人を思いやれること
・見返りを求めない優しさが、奇跡を生む
【🪶連想する四字熟語 】
🔶温良恭倹(おんりょうきょうけん)
意味:穏やかで優しい人柄・礼儀正しく控えめな態度
→おじいさんとおばあさんの人柄そのもの
🔶無欲恬淡(むよくてんたん)
意味:欲がなく、心穏やか
→見返りを求めず善行をする姿勢
ぶんぶくちゃがま

むかしむかし、骨董好きの和尚さんが、古道具屋で立派な茶釜を手に入れました。
ところがその茶釜、火にかけたら動き出し、なんと手足としっぽが生えて歩き出してしまいました。実はそれ、たぬきが化けた茶釜だったのです。
和尚さんは気味悪がって茶釜を古道具屋に売ってしまいます。
するとその夜、茶釜が古道具屋に語りかけ、「私はたぬきです。綱渡りの芸ができます。見世物にすれば儲かりますよ」と言います。
古道具屋は茶釜の言葉に従い、見世物小屋を開くと大盛況。たぬきの芸は評判となり、古道具屋は大金持ちになりましたとさ。
【🌱 教 訓 】
・信頼と協力が、思いがけない幸運を生む。
・知恵と工夫で人の役に立てる。
【🪶連想する四字熟語 】
🔶報恩謝徳(ほうおんしゃとく)
意味:受けた恩義に対して感謝の気持ちを持ち、お返しをすること。
→古道具屋の親切にたぬきが報いる姿勢。
🔶奇想天外(きそうてんがい)
意味:思いもよらない奇抜な発想
→茶釜が綱渡りするというユニークな展開

別の「ぶんぶくちゃがま」の絵本読んだら、続きがあった…!!!
茶釜からタヌキの姿に戻れなくなって、最後病死→もとの寺へ(;゚Д゚)
こぶとりじいさん

昔々、隣同士に住む二人のおじいさんがいました。
ひとりは陽気で優しい性格、もうひとりは欲深くて意地悪な性格。どちらも頬に大きなこぶを持っていました。
ある日、陽気なおじいさんが山で雨宿りしていると、鬼たちが現れて酒盛りを始めます。
おじいさんは怖がるどころか、楽しそうに踊りを披露。鬼たちはおじいさんを気に入り、「また来い」と”こぶ”を人質ならぬ「物質」とします。
それを聞いた欲深いおじいさんは、自分もこぶを取ってもらおうと鬼のもとへ。
しかし踊りは下手で、鬼たちは怒って、なんともう一つこぶをつけてしまいました。
【🌱 教 訓 】
・他人をうらやまず、自分らしく前向きに生きることが大切。
・欲を出して人のまねをすると、かえって不幸を招く。
・素直で陽気な心が、思いがけない幸運を呼び込む。
【🪶連想する四字熟語 】
🔶無欲恬淡(むよくてんたん)
意味:欲がなく、心穏やか。
→欲を出さず自然体でいたおじいさんの姿勢
🔶善因善果(ぜんいんぜんか)
意味:良い行いが良い結果を生む
→陽気なおじいさんの善行が報われる

人生、楽しんだもん勝ち!?
三まいのおふだ

ある日、小僧が一人で山へ栗拾いに出かけることになり、和尚さんは三枚のお札を渡します。
山で夢中になっているうちに日が暮れ、道に迷った小僧は、親切そうなおばあさんの家に泊まることに。
ところがそのおばあさんは、恐ろしい山姥だったのです。
夜中に食べられそうになった小僧は、もらったお札を一枚ずつ使って逃げます。
3枚のお札は大きな川・大きな炎・大きな山となって山姥を足止め。
なんとかお寺に逃げ帰ると、和尚さんが山姥を豆粒に変えて、しっかり封じ込めてしまいました。
【🌱 教 訓 】
・知恵と冷静さが、どんなピンチも乗り越える力になる。
・上っ面の優しさに騙されないで。
・事前の備え(お札)と信頼できる人の助け(和尚さん)が命を守る。
【🪶連想する四字熟語 】
🔶臨機応変(りんきおうへん)
意味:すばやく適切な判断や対応をすること
→小僧の逃げ方と和尚さんの知恵。
🔶知恵才覚(ちえさいかく)
意味:知恵と工夫で物事を解決する力
→小僧と和尚さんの行動全般

山姥(やまんば)って、何にでも変身できるって。東洋の魔女!?
へっこきよめさま

働き者のお嫁さんが、おならを我慢して体調を崩してしまいます。
お姑さんに「遠慮せずにしなさい」と言われて思いきってすると、勢いで家族みんな吹っ飛んでしまい、里に返されてしまいます。
帰り道、お嫁さんは困っている旅人を助け、おならで木の実を落として感謝され、大金をもらいます。
それを見た若者は「こんなに役立つ嫁さんを返すのはもったいない」と思い直し、ふたりは仲良く暮らしました。
【🌱 教 訓 】
・自分らしさを隠さず、素直に打ち明けることが大切。
・恥ずかしいと思うことも、見方を変えれば人の役に立つ。
・受け入れる心が、関係をあたたかくする。
【🪶連想する四字熟語 】
🔶一芸一能(いちげいいちのう)
意味:ひとつの特技でも大きな価値がある
→おならという“特技”が人の役に立つ。
🔶天真爛漫(てんしんらんまん)
意味:自然体で明るくのびのびしていること
→よめさまの明るい性格が家族を笑顔にしてる?

部屋(へや)の由来は、屁屋(へや)だったとか!?( *´艸`)
いなばのしろうさぎ

昔々、八十人の神々が因幡の国のお姫様に求婚するため旅をしていました。
その中に、末っ子で荷物持ちをしていたオオクニヌシという神様がいました。
旅の途中、毛をむしられて苦しんでいる白うさぎに出会います。
兄たちの神々は「海水を浴びて風に当たれば治る」と嘘を教え、うさぎはさらに傷を悪化させてしまいます。
そこへオオクニヌシが通りかかり、やさしく声をかけて正しい治し方を教えます。
うさぎは元気を取り戻し、「あなたこそ姫と結ばれるでしょう」と予言します。
その後、オオクニヌシは本当に姫と結ばれ、やがて偉大な神様として知られるようになりました。
【🌱 教 訓 】
・やさしさと誠実さは、見返りを求めずとも報われる
・弱い者に寄り添う心が、真の強さにつながる
・嘘や意地悪は、結局自分の価値を下げてしまう
・外見や立場ではなく、心のあり方が人を輝かせる
【🪶連想する四字熟語 】
🔶善因善果(ぜんいんぜんか)
意味:善い行いが善い結果を生む。
→大国主神が白兎を助けたことで、白兎が予言を授ける展開。
🔶一視同仁(いっしどうじん)
意味:誰にでも平等に親切にする
→弱ったうさぎにも分け隔てなく接する

オオクニヌシと言えば、島根県の出雲大社の神様だね!
オオクニヌシさん出てくる「古事記」の神様たちの対決すごく好き。
息子も読み聞かせすると爆笑してます
ゆきおんな

冬の夜、吹雪の中で山小屋に泊まった巳之吉と茂作。そこへ現れた雪女が茂作を凍らせ、巳之吉には「見たことを誰にも話すな」と言って去っていきます。
数年後、巳之吉は美しい女性・お雪と結婚し、幸せに暮らしていました。
ある夜、昔の雪女の話をうっかり語ってしまうと、お雪は「私こそ雪女。約束を破ったから殺さねばならぬ」と言います。
けれど子どもを思う気持ちから、巳之吉を許し、お雪は静かに姿を消しました。
【🌱 教 訓 】
・約束は、どんなに時が経っても守るべきもの
・優しさと恐ろしさは、紙一重の存在である
・愛する人を思う気持ちは、時に運命を変える力になる
【🪶連想する四字熟語 】
🔶冷酷無情(れいこくむじょう)
意味:感情を持たず冷たく見える態度。
→巳之吉が初めて雪女にあった時はこんなイメージ
🔶因果応報(いんがおうほう)
意味:行いに応じた結果が返る
→約束を破ったことで訪れる別れ。

母性感じたわぁ
おむすびころりん

むかしむかし、心のやさしいおじいさんが、山へしば刈りに出かけました。
おばあさんが作ってくれたおむすびを食べようとしたとき、ひとつがコロコロ転がって穴の中へ。すると、「おむすびころりんすっとんとん♪」と楽しげな歌が聞こえてきます。
気になったおじいさんが穴をのぞくと、うっかり落ちてしまい、そこには白いネズミたちがいて、おむすびで餅つきをしていました。
おじいさんはネズミたちと楽しく過ごし、お礼に「大きいつづら」と「小さいつづら」から好きな方を選ぶよう言われ、小さい方を持ち帰ります。
家で開けると、中には宝物がいっぱい。おじいさんとおばあさんは幸せに暮らしました。
それを聞いた隣の欲張りなおじいさんも真似をしますが、ネズミたちに無礼な態度をとったため、何ももらえず、穴から出られなくなってしまいました。
【🌱 教 訓 】
・正直でやさしい心が、思いがけない幸せを呼び込む
・欲張ると、かえって大切なものを失ってしまう
・人との関わりには、感謝と礼儀が大切
【🪶連想する四字熟語 】
🔶善因善果(ぜんいんぜんか)
意味:良い行いが良い結果を生む。
→やさしいおじいさんが宝物を得る。
🔶自業自得(じごうじとく)
意味:自分の行いの結果は自分に返る
→欲深さが招いた結末。
ももたろう

むかしむかし、川から流れてきた大きな桃を、おばあさんが拾って家に持ち帰ると、中から元気な男の子が出てきました。
桃から生まれたその子は「桃太郎」と名付けられ、おじいさんとおばあさんに大切に育てられます。
桃太郎は立派に成長し、鬼ヶ島へ悪い鬼を退治しに行くことを決意。
おばあさんが作ってくれたきびだんごを持って旅に出ると、途中で犬・猿・キジに出会い、仲間になります。
力を合わせて鬼ヶ島へ向かい、鬼たちと戦い、ついに勝利。
鬼から奪われていた宝物を取り戻し、村に平和をもたらしました。
おじいさんとおばあさんは大喜びし、桃太郎と仲間たちは幸せに暮らしました。
【🌱 教 訓 】
・正義の心と勇気が、困難を乗り越える力になる
・感謝の気持ちと礼儀が、人との信頼を築く
・仲間との協力が、大きな力を生む
【🪶連想する四字熟語 】
🔶勇猛果敢(ゆうもうかかん)
意味:勇ましく、決断力がある。
→鬼退治に向かう桃太郎の姿勢。
🔶協力一致(きょうりょくいっち)
意味:力を合わせて物事に取り組む。
→犬・猿・キジとのチームワーク。

「鬼の視点から見る桃太郎」の絵本もあって、そっちも面白い発見があるよ!
最後に
昔話って、やっぱり奥が深い。
こども向けと思っていた物語が、実は大人の心にも響く。
そんな発見がたくさんありました。
教訓や四字熟語を通して見えてくるのは、
時代が変わっても変わらない
・人との関わり方
・心のあり方。
親子で物語を味わいながら、やさしさや知恵を少しずつ育てていく。
そんな時間が、きっと未来の人間関係づくりにもつながっていくはずです。

今日の昔話が、誰かの心にそっと残りますように。
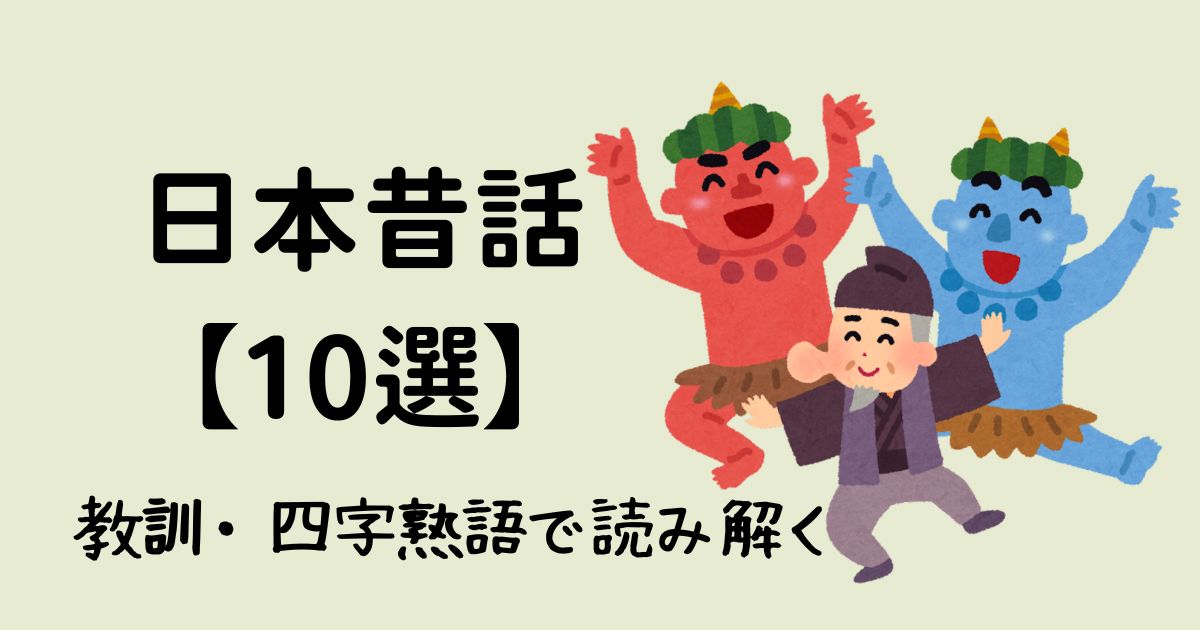

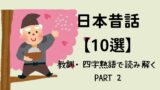


コメント