
こんにちは、りんむです。
子どもにとって料理をする事ってどんな効果があるの?
私はこれまで、発達障害に関する多くの専門書に目を通してきましたが、その中には「料理」を発達支援の一環として積極的に推奨する著者が少なくありません。
料理という行為は、認知・感覚・運動の統合的な働きを促すだけでなく、自己肯定感や主体性の育成にも寄与するとされています。
では、なぜ料理が発達の促進に効果的だと言われるのでしょうか?
料理をすることで得られる5つの効果とは?

「料理」は日常の中でできる最高の発達支援ツールなんですよ!
🧠 脳の発達を促す
・調理中は「段取り」「判断」「注意」「推測」など、前頭前野(特に背外側前頭前野)が活性化。
・この部位は記憶・理解・戦略的思考を担い、学習能力や集中力にも関係します。
・実際に親子でホットケーキを作るだけでも脳活動が高まるという研究結果あり。
👀 感覚統合を育む
・料理は五感(触覚・嗅覚・視覚・聴覚・味覚)を同時に使う。
・感覚過敏や偏食のある子にも、調理を通じて食材への抵抗感が減ることが報告されている。
💬 自己肯定感・達成感が育つ
・「できた!」という成功体験が、自己効力感や自信につながる。
家族に「ありがとう」「美味しい」と言われることで、役に立っている実感も得られる。
👨👩👦 親子の絆が深まる
・一緒に作業することで、自然な会話や協力が生まれ、信頼関係が強まる。
・共食(家族で一緒に食べること)にもつながり、幸福感や安心感が高まる傾向も。
🌱 生きる力・社会性が育つ
・段取りや役割分担を通じて、仕事に必要な力(計画性・判断力・協調性)も身につく
・食材や調理法を通じて、自然や人への感謝の気持ちも育まれる。
まとめ

料理という行為は、発達支援の領域において極めて多面的な効果を有する事がおわかりいただけたでしょうか?
計画性の育成、巧緻性の向上、感覚統合の促進、社会的コミュニケーション、そして「できた!」という達成感。どれをとっても、子どもの発達において無視できない要素ばかりです。
まるで一皿の料理に、認知心理学と運動学と教育学がギュウギュウに詰め込まれているようなもの。おいしさだけでなく、成長まで味わえるなんて、なんとも贅沢。
発達支援としての料理は、いわば“学びのフルコース”なのかもしれません。
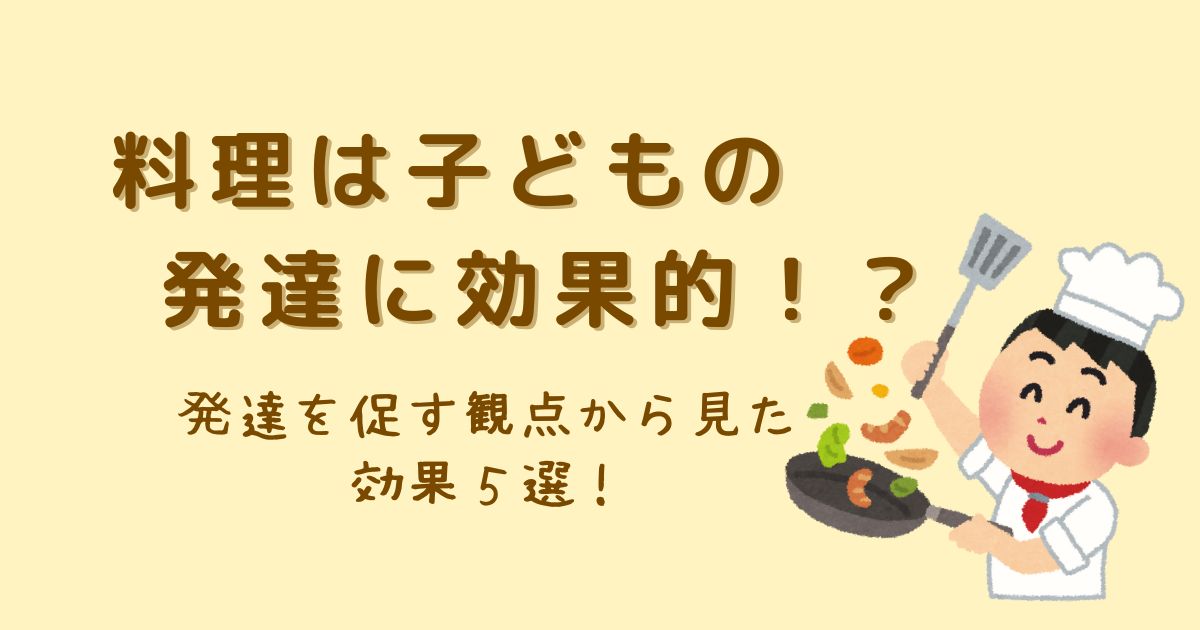


コメント