
こんにちは、りんむです。
発達に関する病院・支援の記録をここに残しています。
日々、いろいろな支援先へ相談に行ったり、サポートを受けたりしています。その記録を、備忘録として残していこうと思います。
発達障害発覚までの道のり
上記記事より👇
- 5歳年中さん時の担任より
「どんくさい」と言われる。
- 6歳年長さん時の担任より
「一つなら分かるが、複数の指示は理解できていない様子」と指摘有。
→役所へ相談(まだ大丈夫と言われる) - 7歳小学1年生担任より
(夏休み前の懇談会にて)
理解が出来ていないけど、なんとか通常級で大丈夫。 - 7歳息子の状態を調べ「視知覚」が気になる
本で調べビジョントレーナーさんの所へ行く。
検査の項目の幾つかが、年齢以下である事が発覚。 - 7歳小学1年生担任より
(冬休み前の懇談会にて)
スクールカウンセラーさんへ相談することを提案される。 - 8歳スクールカウンセラーさんへ相談
愛知県青い鳥医療療育センターへ行くことを提案される。
- 8歳愛知県青い鳥医療療育センターへ
検査の結果「境界知能」であることが発覚。
病院・支援の記録
「発達障害発覚までの道のり」と重複する部分有ります。
ここでは、病院・支援の記録を残しています。
- 2022/8【小学1年生】
視知覚検査を受け、結果をもらう見ていて痛々しい程に、息子の心がボロボロになっていた。
- 2022/11ビジョントレーニング1回目
やさしいトレーナーさんなので、息子は通うのを楽しみにするようになる
- 2023/3ビジョントレーニング2回目
- 2023/3医療療育センター【初診】
- 2023/4【小学2年生】
医療療育センター【知能検査】 - 2023/5医療療育センター【検査結果】
境界知能である事が分かる
- 2023/7ビジョントレーニング3回目
- 2023/8医療療育センター【経過観察1回目】
- 2023/9小学校にて「通級」へ通い始める
授業をサボれるから、通級好きって言ってた
- 2023/11医療療育センター【経過観察2回目】
- 2023/12ビジョントレーニング4回目
- 2024/12医療療育センター【経過観察3回目】卒業
- 2024/3ビジョントレーニング5回目
自宅でするトレーニングを息子が嫌がり、親子共にやる気を失う…。
- 2024/3小学校の「通級」終了
本人が嫌がったので、3年生からは辞めた
- 2024/8【小学3年生】
「イノチグラス」を作ってもらう - 2024/8発達支援コーチ セッション1回目
この頃から、学校へ行くことに抵抗が無くなり始めた!?
- 2024/9発達支援コーチ セッション2回目・卒業
セッションは卒業しましたが、教えて頂いた支援方法を日々実践中
- 2025/7【小学4年生】
担任より、「学校が大好きな子ですね」と言われる!
ビックリ・嬉しすぎで絶句 Σ(゚Д゚) - 2025/8療育整体を息子に開始する
※講座を受講し「療育整体師」になった
- 2025/9栄養療法をはじめる
高|タンパク・鉄分・ビタミン。低|糖質に。
まとめ
2025年9月現在、私は以下の2つを大切にしながら日々を過ごしています。
- 発達支援コーチ
→子どもが「やりたい!」と思う遊びを、全力で一緒に楽しむこと。
これは本当に、息子の心を元気にしてくれたと感じています。 - 療育整体
→子どもの身体を整えることで、自然と発達を促すアプローチです。
神経に問題があるなら、そこに伴走する血流を良くすることで、発達障害は改善できる。
毎日少しずつ、息子の身体に整体を施すだけ。
しっかり身体を整えて、知的障害の改善につなげたいと願っています。
「発達障害を治したい」と本気で取り組んでいる人は、世の中にたくさんいます。
私は、そんな方々が発信する情報を、これからも取りこぼさないように拾い続けていきたい。
そして、自分自身の学びと実践を通して、息子の未来に少しでも光を届けられるよう、これからも歩み続けます。
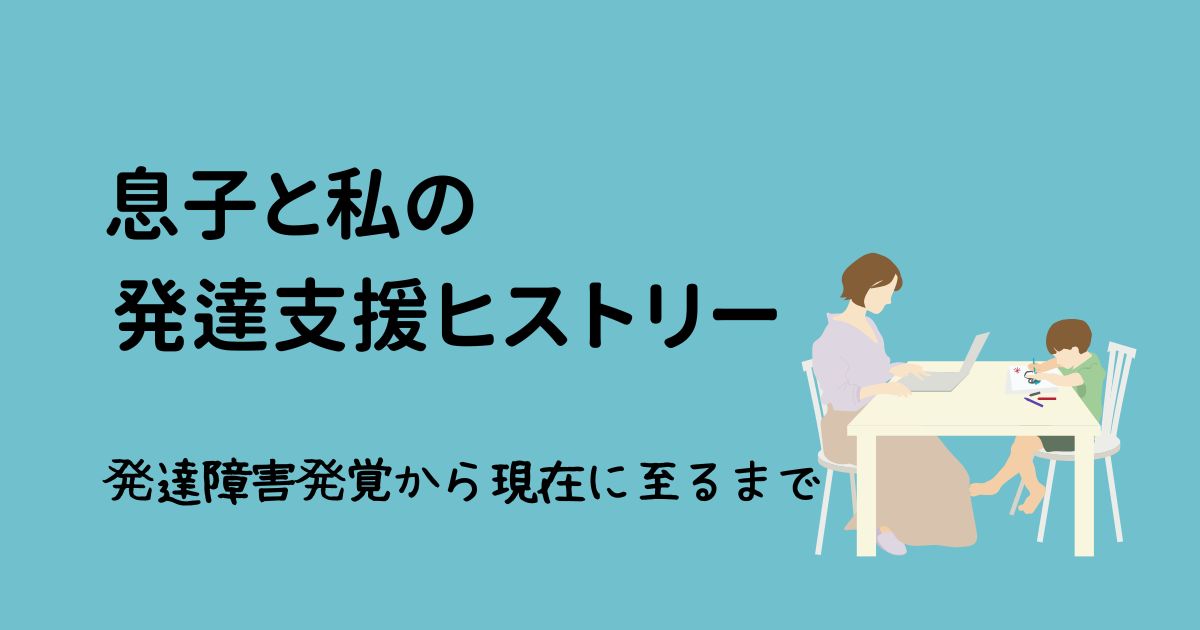
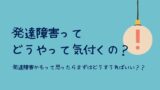
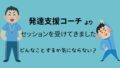
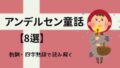
コメント