
こんにちは、りんむです。
日本昔話って意外に本当は”怖い”お話ありますよね。
昔話って、ただの“お話”じゃない。
こどもに伝えたいこと、大人が忘れかけていたことが、そっと語られている気がします。
「やさしさって何?」
「正直でいるってどういうこと?」
そんな感性を、物語を通してこどもに届けてみませんか。
今回は、子育てに役立つ日本昔話を10話(PART2)選び、それぞれのあらすじ・教訓・連想される四字熟語をやさしくまとめました。
親子で読んでも、大人が心の整理に使っても、きっと何かが響くはずです( *´艸`)
うりこひめとあまのじゃく

むかしむかし、子どもがいないおじいさんとおばあさんのもとに、川から流れてきた瓜の中から女の子が生まれました。名前は「うりこひめ」。
美しく、機織りが上手なうりこひめは、村でも評判の娘に育ちます。
ある日、おじいさんとおばあさんが出かける際、「誰が来ても戸を開けてはいけないよ」と言い残します。
しかし、アマノジャクが言葉巧みにうりこひめをだまし、外へ連れ出してしまいます。
その後、アマノジャクはうりこひめになりすまそうとしますが、正体がばれて罰を受ける結末となったとさ。
【🌟 教 訓 】
・見た目や言葉に惑わされず、本質を見抜く力が大切
・油断は思わぬ危険を招く
・約束を守ることは、自分を守ることにつながる
・悪事はいつか必ず明るみに出る
【🧠連想する四字熟語 】
🍈油断大敵(ゆだんたいてき)
意味:油断すると大きな失敗につながる
→戸を開けてしまったうりこひめ
🍈因果応報(いんがおうほう)
意味:行いに応じた結果が返る
→アマノジャクが罰を受ける

地域によっては、うりこひめが殺されてしまう結末もあるんだって…。
かちかち山

むかしむかし、畑を荒らすたぬきをおじいさんが捕まえました。
ところが、たぬきはおばあさんをだまして縄をほどかせ、ひどいことをして逃げてしまいます。
それを知ったうさぎは、おじいさんのためにたぬきに仕返しを決意。
たぬきの背負った柴に火をつけたり、唐辛子みそを薬だと偽って塗ったり、最後には泥舟に乗せて海へ出て沈めてしまいます。
うさぎは、悪いことをしたたぬきにきちんと罰を与え、おじいさんの悲しみを晴らしました。
【🌟 教 訓 】
・悪いことをすれば、必ずその報いを受ける
・正義とは、誰かのために勇気を出すこと
・嘘や裏切りは、人の信頼を失う
・優しさだけでなく、厳しさも時には必要
【🧠連想する四字熟語 】
🔥勧善懲悪(かんぜんちょうあく)
意味:善をすすめ、悪をこらしめる
→うさぎがたぬきを懲らしめる姿勢
🔥自業自得(じごうじとく)
意味:自分の行いの結果は自分に返る
→たぬきの最期に通じる教訓

このお話も絵本によっては、おばあさん殺されちゃってる…。
花さかじいさん

むかしむかし、心のやさしいおじいさんとおばあさんが、かわいがっていた犬のシロと仲良く暮らしていました。
ある日、シロが「ここ掘れワンワン」と鳴いた場所を掘ると、たくさんの宝が出てきます。
それを見た隣の欲張りなおじいさんは、シロを無理やり借りて同じように掘らせますが、出てきたのはゴミばかり。怒ってシロを殺してしまいます。
悲しんだやさしいおじいさんは、シロの灰をまいて「枯れ木に花を咲かせましょう」と言うと、見事に桜が満開に。
その姿を見た殿様は感動し、おじいさんに褒美を与えます。
欲張りなおじいさんも真似をしますが、灰をまいても花は咲かず、殿様に怒られてしまいました。
【🌟 教 訓 】
・やさしい心は、思いがけない幸せを呼び込む
・欲張りやねたみは、自分を不幸にしてしまう
・人のまねをしても、心が伴わなければ結果はついてこない
・善意には報いがあり、悪意には罰がある
【🧠連想する四字熟語 】
🌸善因善果(ぜんいんぜんか)
意味:良い行いが良い結果を生む
→シロを大切にした心が花を咲かせる
🌸因果応報(いんがおうほう)
意味:行いに応じた結果が返る
→ねたみの心が自分に返ってくる

このお話では、おじいさんの犬が殺されちゃった😿
さるかにがっせん

ある日、さるは柿の種を持っていて、かにはおにぎりを持っていました。
さるは「柿の種は木になって実がなるから、おにぎりよりずっといい」と言って、かにをだまして交換させます。
かには一生懸命に柿の木を育て、実がなるのを楽しみにしていました。
でも木に登れないかには、さるに実を取ってもらおうと頼みます。
ところがさるは熟した実を独り占めし、青い実をかにに投げつけカニを傷めつけます。
その後、かにの子どもたちは、ハチ・クリ・うす・牛のふんなどの仲間と協力して、悪いさるをこらしめます。
最後には、さるは仲間たちの知恵と力で退治され、かにの仇討ちは果たされました。
【🌟 教 訓 】
・嘘やずるさは、いつか自分に返ってくる
・弱い立場でも、知恵と協力で困難に立ち向かえる
・親子の絆は、時代を超えて尊いもの
・正義は、力ではなく思いやりと知恵で守られる
【🧠連想する四字熟語 】
🦀協力一致(きょうりょくいっち)
意味:力を合わせて物事に取り組む
→仲間たちの連携プレー
🐵勧善懲悪(かんぜんちょうあく)
意味:善をすすめ、悪をこらしめる
→さるの悪事が罰を受ける

このお話では、カニのお母さんが…。
したきりすずめ

むかしむかし、心のやさしいおじいさんと、欲張りなおばあさんが暮らしていました。
ある日、おじいさんがかわいがっていたすずめが、おばあさんの作った糊を食べてしまいます。
怒ったおばあさんは、すずめの舌を切って追い出してしまいました。
おじいさんは心配になり、山奥の「すずめのお宿」へすずめを探しに行きます。
すずめはおじいさんの優しさに感謝し、おもてなしのあと「小さいつづら」と「大きいつづら」から好きな方を選ばせます。
おじいさんは小さい方を選び、家に帰って開けると中には宝物がいっぱい。
それを知ったおばあさんは、自分も欲しくなってすずめのお宿へ向かい、大きいつづらを強引に持ち帰ります。
ところが、途中で開けてしまうと中からお化けや毒虫が飛び出し、おばあさんは驚いて逃げ帰ることになりました。
【🌟 教 訓 】
・欲張りすぎると、かえって不幸を招く
・謙虚でやさしい心は、思いがけない幸せを呼び込む
・人のまねをしても、心が伴わなければ報われない
・善行には報いがあり、悪意には罰がある
【🧠連想する四字熟語 】
🐦善因善果(ぜんいんぜんか)
意味:良い行いが良い結果を生む
→おじいさんの優しさが宝物につながる
✂️因果応報(いんがおうほう)
意味:行いに応じた結果が返る
→おばあさんの欲深さが罰を招く

わざわざ小さな小さな舌を切らなくても…。
いっすんぼうし

むかしむかし、子どもがいないおじいさんとおばあさんが、神さまに「親指ほどの子でもいいから授けてください」とお願いしました。
すると本当に小さな男の子が生まれ、「一寸法師」と名付けられました。
一寸法師は成長しても小さいままでしたが、心は大きく、武士になる夢を持っていました。
ある日、針を刀に、お椀を船に、箸を櫂にして、京の都へ旅立ちます。
都では大臣の屋敷に仕え、姫さまと仲良くなります。
ある日、姫さまと清水寺へ参拝に行く途中、鬼が現れて姫をさらおうとします。
一寸法師は鬼に飲み込まれながらも、針の刀で鬼の体内を刺して大暴れ。
鬼は逃げ出し、打ち出の小槌を落としていきます。
その小槌で願いを叶えた一寸法師は、立派な若者の姿になり、姫さまと結婚。
おじいさんとおばあさんも都に呼び寄せ、みんなで幸せに暮らしました。
【🌟 教 訓 】
・見た目や大きさではなく、心の強さが人を輝かせる
・夢を持ち、努力し続けることで道は開ける
・知恵と勇気があれば、どんな困難にも立ち向かえる
・感謝の気持ちと親孝行の心は、人生を豊かにする
【🧠連想する四字熟語 】
🐣勇猛果敢(ゆうもうかかん)
意味:勇ましく決断力がある
→鬼に立ち向かう姿
🐣七転八起(しちてんはっき)
意味:何度失敗しても立ち上がる
→小ささを乗り越えて夢を叶える
ねずみのよめいり
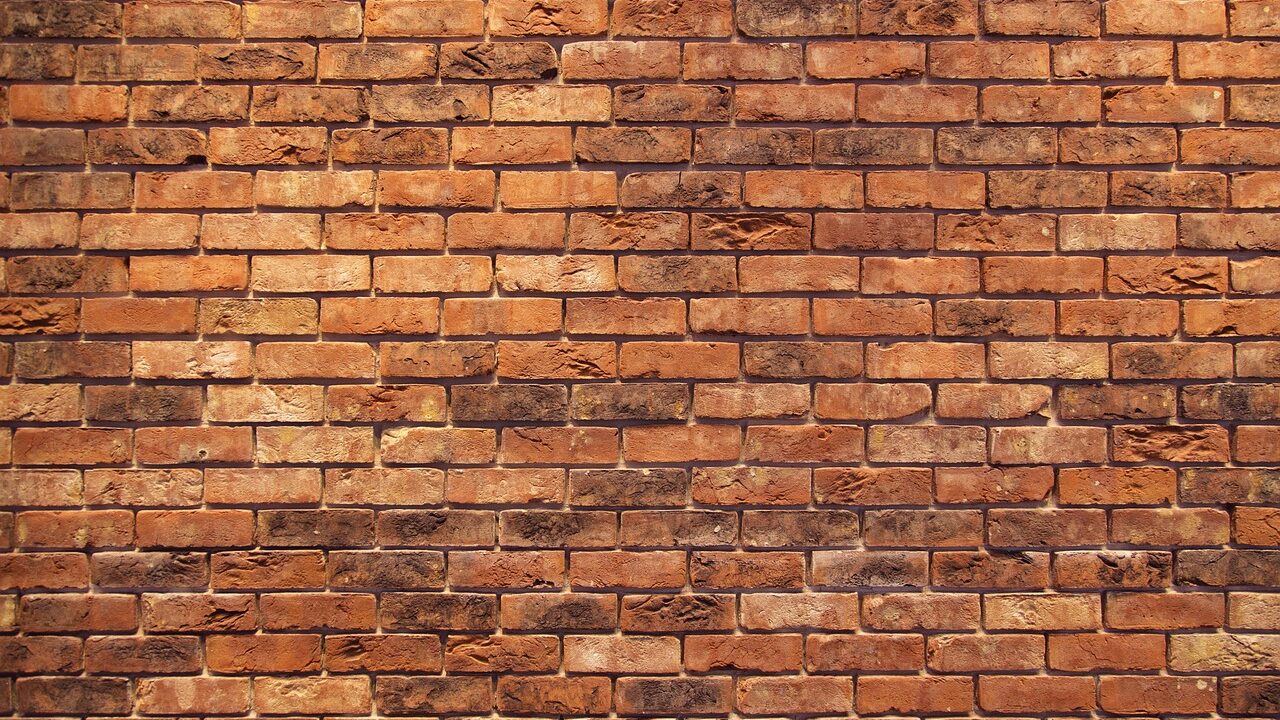
むかしむかし、ねずみの夫婦に、とても美しくて賢い娘がいました。
「この子には世界一えらい者を婿にしたい」と考えた両親は、まず太陽にお願いに行きます。
ところが太陽は「雲にはかなわない」と言い、雲は「風にはかなわない」、風は「壁にはかなわない」、壁は「ねずみに穴を開けられてしまう」と言います。
結局、世界一えらい者は「ねずみ」だったのです。
こうして娘は、同じねずみの立派な若者と結婚し、幸せに暮らしました。
【🌟 教 訓 】
・本当の強さは、見た目や地位ではなく、その場にふさわしい力
・自分たちの中にこそ、価値や可能性がある
・比べすぎず、身近な幸せを大切にすることが大事
・まわりの声を聞きながら、自分の答えを見つけることが大切
【🧠連想する四字熟語 】
🐭本末転倒(ほんまつてんとう)
意味:大事なことを見失う
→外ばかり見て、身近な価値を忘れかける
🐭適材適所(てきざいてきしょ)
意味:その人に合った場所がある
→ねずみ同士の結婚が一番自然
つるのおんがえし

ある冬の日、心やさしいおじいさんが、罠にかかっていた一羽の鶴を助けます。
その夜、美しい娘が「道に迷いました」と訪ねてきて、おじいさんとおばあさんは泊めてあげます。
娘は家事を手伝いながら暮らし、ある日「布を織りたいので糸を買ってください。織っている間は絶対に部屋をのぞかないでください」と言います。
娘が織った布はとても美しく、高く売れて、おじいさんたちは豊かになっていきます。
しかし、娘は日に日にやつれていき、心配になったおじいさんとおばあさんは、ついに部屋をのぞいてしまいます。
そこには、自分の羽を抜いて布を織る鶴の姿が──。
娘は、かつて助けてもらった鶴であり、恩返しのために人間の姿で来ていたのです。
「姿を見られてしまったので、もうここにはいられません」と言い残し、鶴は空へ帰っていきました。
【🌟 教 訓 】
・やさしさは、思いがけない形で返ってくることがある
・約束は、どんなに親しい間柄でも守るべきもの
・無理をして続ける関係は、いつか壊れてしまう
・相手の気持ちを思いやることが、本当の優しさにつながる
【🧠連想する四字熟語 】
🧵報恩謝徳(ほうおんしゃとく)
意味:受けた恩や徳に感謝し、それにふさわしい形で報いる
→命を削っても恩返しがしたかった鶴
🧵自業自得(じごうじとく)
意味:自分の行いの結果は自分に返る
→約束を破ったことで別れが訪れる
十二支のはじまり

むかしむかし、神さまが「新年のあいさつに早く来た順に、一年の大将にする」と動物たちに伝えました。
それを聞いた動物たちは、「一番乗りになるぞ!」と大騒ぎ。
牛は足が遅いことを気にして、前の晩から出発。
その背中にこっそり乗っていたのが、ずる賢いねずみ。
神さまの門が開くと、ねずみは牛の背中から飛び降りて一番乗り!
こうして、ねずみが最初の干支となり、牛・虎・うさぎ…と順番が決まっていきました。
ちなみに、猫はねずみに「新年のあいさつは1月2日だよ」と嘘を教えられ、間に合わず干支に入れませんでした。
それ以来、猫はねずみを追いかけるようになったとか──。
【🌟 教 訓 】
・努力することは大切だけど、ずるさで勝つこともある
・嘘は人を傷つけ、信頼を失う
・それぞれの個性が、役割や順番を決める
・競争の中でも、工夫や知恵が力になる
【🧠連想する四字熟語 】
🐮十人十色(じゅうにんといろ)
意味:人それぞれに個性がある
→出発するタイミングは、はみんな違う
🐯機略縦横(きりゃくじゅうおう)
意味:状況に応じて柔軟に知恵を働かせる力を表す
→ねずみの作戦勝ち
せつぶんのおはなし

むかしむかし、長く雨が降らず、村の人々は困っていました。
鬼が「娘を差し出せば、雨を降らせてやろう」と提案してきます。
ととさま(父)は悩みながらも、末娘のおふくを鬼のもとへ送る決心をします。
おふくは怖がりながらも、村のために鬼のもとへ向かいます。
鬼の屋敷への道すがらははさま(母)から渡された花の種をまき、春になる頃その花をたどって家にこっそり帰ります。
鬼が追ってきますが、母さまの知恵で追い返すことに成功しましたとさ。
【🌟 教 訓 】
・大切な人を守るために、勇気を出すことができる
・知恵と冷静さは、困難を乗り越える力になる
・行事の背景には、人々の願いや祈りが込められている
【🧠連想する四字熟語 】
👹勇気凛々(ゆうきりんりん)
意味:恐れず勇ましい心
→おふくの行動そのもの
👹深謀遠慮(しんぼうえんりょ)
意味:深く考え、遠い先まで見通して計画を立てること
→かかさまが持たせた種のおかげで無事帰還
さいごに
こうして振り返ってみると、昔話って、思った以上に“こわい”ものが多かった。
登場人物が命を落としたり、だまされたり、罰を受けたり──
子ども向けと思っていた物語の中に、容赦ない展開がいくつもありました。
でもその“こわさ”の奥には、
人の弱さや欲、そしてそれを乗り越える知恵や勇気が描かれていて。
だからこそ、何百年も語り継がれてきたのかもしれません。
やさしさだけじゃない。
痛みや葛藤も含めて、昔話は“生きること”そのものを教えてくれる気がします。
読んでくれた誰かの心に、そっと残る物語がありますように。
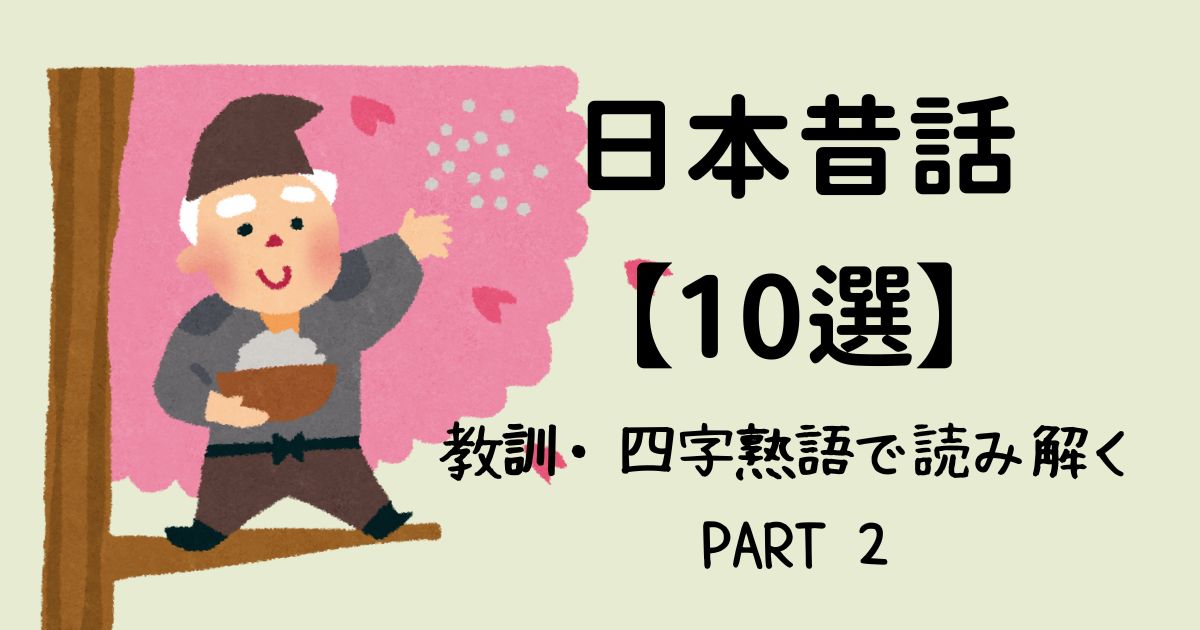

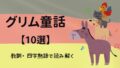
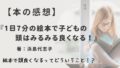
コメント