
こんにちは、りんむです。
発達障害かもと思ったらすぐにこの5冊を順番に読んで欲しい!
「発達障害境界知能」と診断されたとき、私の頭の中は真っ白になりました。
“この子は一生、困りごとを抱えて生きていくの?”
“私に何ができるんだろう?”
そんな不安と焦りの中で、私は本を読み漁り、情報を探し続けました。
でも、病院や学校では「様子を見ましょう」と言われるばかり。
グレーゾーンの子には、明確な支援の道筋が示されないことも多いのです。
だからこそ、私は「家庭でできる支援方法」を知りたかった。
そして、実際に試してみて、息子の笑顔が少しずつ増えていくのを感じました。
この記事では、私が出会った「読んでよかった!」と思える本を5冊紹介します。
どれも、発達障害やグレーゾーンの子どもを支えるために、家庭でできる具体的な方法が書かれている本ばかりです。
同じように悩む方の、希望の一歩になれば嬉しいです。
発達障害の症状とは?子どもに寄り添うおすすめの1冊
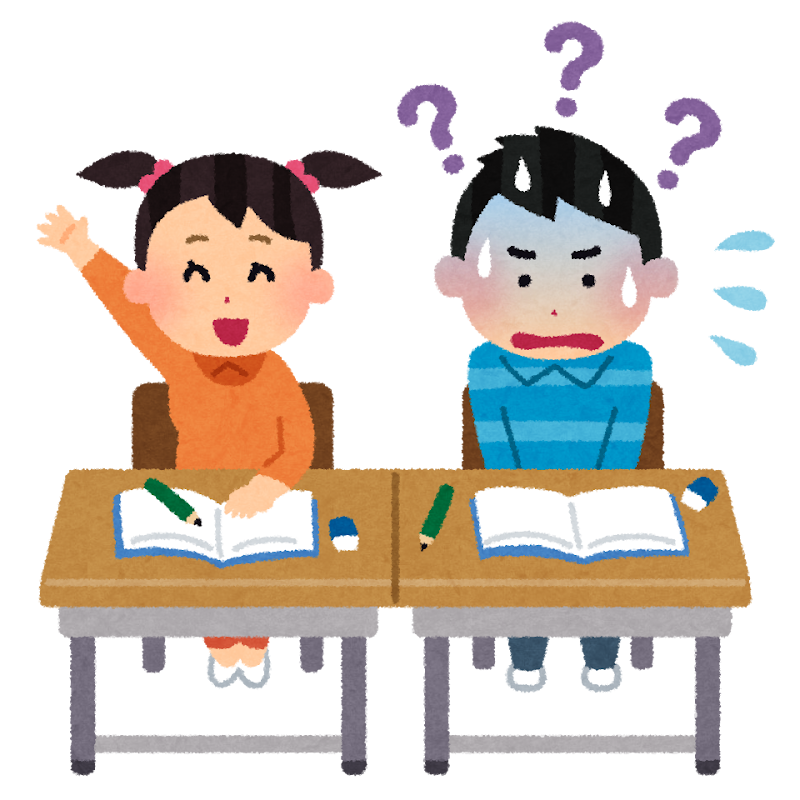

発達障害のある子どもが日常でどんなことに困っているのか——
まずは、子どもの心理を知っておくと、支援の仕方が大きく変わります。
たとえば、こんな行動に心当たりはありませんか?
・なぜ過度に弱気になっているのか?
・なぜすぐイライラしてしまうのか?
・椅子に座っていられないのはなぜ?
・わがままに見えるのはどうして?
・こだわりが強すぎる理由は?
保護者からすると「困った態度」に見える行動も、実はちゃんと理由があります。
それは、言葉でうまく表現できないだけだったり、感覚や環境への過敏さだったり。
子どもの行動の背景を知ることで、見守る側の思考パターンが変わり、親子の関係がぐっと良くなることもあるのです。
そんな気づきを与えてくれたのが、次に紹介する1冊です
1冊目:『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた声掛け接し方大全集』
発達障害やグレーゾーンの子どもが日常生活の中で何を感じ、どんなことで困っているのかを、保護者の視点ではなく子ども自身の視点から教えてくれます。
読んでみると、「うちの子、こんなふうに感じていたのか…」と驚くことばかり。
そして、声かけや接し方を少し変えるだけで、子どもの表情や行動が変わることを実感しました。
この本を読んだ後では、支援する保護者としての私自身の気持ちがまったく違います。
「何かしてあげなきゃ」ではなく、「一緒に歩んでいこう」という気持ちになれました。
家庭でできる発達障害支援|実践した本4冊を紹介
書店へ行き、発達障害についての本を買いあさり読んで行くと
障害受容・周りの合理的配慮が必要
ほとんどの本にこんな感じの事が書かれていて、かなり落ち込んだことを覚えています。

息子は一生「発達障害」を背負って生きていくんだ。境界知能だから、一見普通に見えるけど本当は身体も心も通常発達児に比べて毎日ヘトヘトになってる。
でも、疲れている事すら誰からも気付いて貰えない。
| 障害受容 | 発達障害は治らないから、障害を持っていることを保護者は受け入れなさい。 |
| 合理的配慮 | 発達障害である人の特性を理解し、周りの人がその人が生きていきやすいように配慮すべきだ。 |
私は、医師や専門家の方々からの話、これらの本の内容を信じ息子の障害を受け入れ、彼がどうしたら笑顔で生活できるのかを考えました。そして、息子の周りの保護者にもそれらを伝え、配慮してくれるよう伝えていました。でも…

やっぱり息子が発達できないと信じたくない。
自分の力で生きていけるようにしてあげたい!
「発達障害は脳機能の問題だから、発達しない」と思い込んでいたのが間違いだったことを教えてくれた厳選した4冊を紹介します👇
2冊目:『人間脳を育てる 動きの発達&原始反射の成長』(灰谷孝)

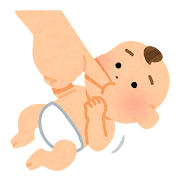
原始反射の統合遊びで、発達をうながす!
「原始反射の統合というアプローチ」を通じて、脳と身体のつながりを整えることで発達を促す方法が紹介されています。
原始反射とは、赤ちゃんの頃に自然に現れる反応のこと。
本来は成長とともに消えていくはずの反射が残っていると、学習や感情のコントロールに影響を与えることがあるそうです。
この本を読んでから、発達支援コーチのセッションを受けたり、家庭でもできる動きのサポートを取り入れたりしました。
すると、息子が学校へ笑顔で行ける日が増えてきたんです。
3冊目:『NEURO 神経発達障害という突破口』(浅見淳子)
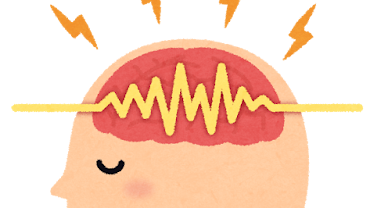
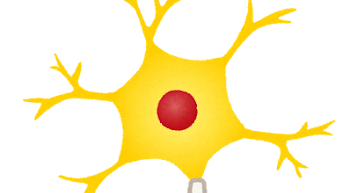
発達障害は治る時代になりました。けれども治すのは医療ではないこともはっきりしてきた。
NEURO神経発達障害という突破口77頁
発達障害は「神経発達症」であるという視点を教えてくれた本👆
神経に働きかけることで、発達は促せるという希望をもらいました。
【これまで】幼児期、小児期または青年期に初めて診断される障害
NEURO神経発達障害という突破口26頁より
→広汎性発達障害というくくり
→自閉症スペクトラム その他精神遅滞や学習障害がここに入る。
【DSM-5】
神経発達障害
→知的障害、コミュニケーション障害、自閉スペクトラム症、注意欠損・多動性障害、運動障害等
神経発達障害という事は、神経へアプローチすれば発達障害・知的障害等治る!?

わーいわーい!嬉しい!またまた、発達の手がかりを見つけた!!!!
4冊目:『療育整体』(松島眞一)


次は、神経を上手くつなげる方法を教えてくれた本です👇
動脈・静脈も神経支配を受けています。一方で、神経も血管から酸素の供給を受けています。つまり、神経と血管は相互依存関係なんですよ。
療育整体 勝手に発達する身体を育てよう49頁
血流をよくして「つまり」を無くせば、神経も上手くつながり発達する!
そんな流れなんだそうです。これは嬉しい事を教えて貰えました!
そして、療育整体を作った著者:松島眞一さんは家庭でも簡単に療育整体に取り組めるように全国飛び回って講座をしてくれています。

私も講座を受けたけど、ただただ楽しかった!
松島先生はサービス精神旺盛だし、受講者はみんな真剣に子どもの発達を願う人ばかりだから、熱意も一緒でみんなやる気で目がキラキラされてました。
5冊目:『薬に頼らず子どもの多動・学習障害をなくす方法』(藤川徳美)

栄誉の欠如こそが、子どもの発達障害を引き起こす
鉄不足の人は一様にタンパク質不足&糖質過多の傾向にあるため、共に暮らす子どもにも偏りが生じ、発達障害が顕著になってくのです。
薬に頼らず子どもの多動・学習障害をなくす方法 69頁
Σ(゚д゚lll)ガーン
妊娠期に私は完全に「鉄不足」でした。
なんなら出産後の入院中、何度か鉄不足の為注射を打ってもらってました。

私の出す食事は、息子に必要な栄養を全然あげられてなかった。
しかも「超」糖質取りすぎで神経の発達を阻害してたんだΣ(゚д゚lll)ガーン
子どもの問題行動を改善に導く食事の大原則を、改めてお伝えします。
薬に頼らず子どもの多動・学習障害をなくす方法 104頁
①タンパク質を積極的に取る=高タンパク質
②糖質の摂取量を抑える=低糖質
③足りない鉄分を補給する=高鉄分
栄養に関する本を何冊か読んでいたけど、どの本にも共通するのが「糖質を控えましょう!」
食事に対するモチベが180°変わった本です。
・和食=ヘルシーって本当?
・国の勧める栄養バランス(主食(炭水化物)を50~65%)って本当に適切?
真実は…上記の本の中に!
発達障害の子どもに家庭でできる支援を探して|まとめとメッセージ
発達障害グレーゾーン(境界知能)の息子は、学校や病院では「様子を見ましょう」で終わってしまいました。
でも、「様子見」している間にも、息子は日々成長していて、困りごとが自然に解消されるわけではありません。
発達障害と診断された子には「療育」という支援があるようですが、グレーゾーンの子にはその情報すら届かないことが多いのです。
だからこそ、親が自分で調べていかないと、必要な情報はやってきません。
この5冊は、私自身が「息子の発達を諦めたくない」と思い続けて探し、出会った本たちです。
どれも、家庭でできる支援方法が具体的に書かれていて、実際に試して効果を感じたものばかり。
同じように悩む方の参考になれば嬉しいです。



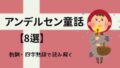

コメント